連載5 沖縄・旧盆のエイサー
第5回 ウークイ・エイサー ~ 暗闇を取り戻す ~

沖縄の夏には、旧盆という大きな節目がある。新盆と同じように、ご先祖さまが帰ってきて数日滞在し、また帰っていく。それだけの出来事だが、ご先祖さまたちが“守り神”の領域に近い沖縄では、年に一度の重要な行事となっている。
旧盆の起源は、まだ人々の生活がそれほどモノに溢れていなかった時代に遡る。「亡くなったひとが、あの世でこの世の親しい人を見守る」というのは、とても個人的な気持ちの反映だ。それが次第に村落共通の儀礼になっていったのではないだろうか。
それは、沖縄でも地域によって旧盆のやり方が違うことから想像できる。森に近いところでは森を通じ、海辺の集落では浜に出て御迎え(ウンケー)と御送り(ウークイ)を行なう。街の場合は、最も身近な宇宙である「そら」を通じてご先祖さまはやってくることが多い。

ペットボトルに入れたロウソクでウンケー。 コザ/2012年
沖縄の旧盆がとても豊かに感じるのは、生きていた頃の面影が、亡くなったあとも続いているような、独特の感覚があるからではないかと思う。日本の各地方にあるような、恐ろしい幽霊話は見当たらない。たしかに沖縄ではヒトは死んだあとは守護神になるのだが、その姿はあくまでも生きているときの延長である。
アジアや大陸の多くの土地と同じように、火葬が奨励されるようになる前は、土葬や風葬が普通だった。その中でも印象深いのは、埋葬して一定の期間が経つとお墓から故人を出し、親族みながそろって宴をひらいたという風習である。
今でもシーミー(清明祭)にはお墓で宴会を行なうが、火葬してすでにお骨になっている。そうではなく、“完全にお骨になっていない期間にも、故人に参加してもらう”という発想には、感動を覚えてしまう。愛情の深さや絆が非常に深く、またおおらかなものだったのだろう。自然の力が色濃かった古代の沖縄では、死はそれほど悲しいものではなかった、とさえ思えてくるのだ。
生と死は別のものではなく、繋がっているもの。樹と土のように、もっと言えば同じもの、お互いになくてはならない存在ではないだろうか。沖縄の古層を探っていくと、そんな感覚をおぼえてしかたがない。

義祖父の匂いが今でも家に残る。
ご先祖さまが帰ってくる道筋はいろいろあって、僕が聞いたものだけでも、海中、海上、空、樹、石など、依りしろは多岐にわたる。いずれも自然物を通じてくる傾向が強い。あの世のことはグソー(後生)と言い、概ね「青い世界」だとされている。赤い夕暮れのあとの、あの青である。
もちろんこれは様々に論じられている世界観の一部だが、僕の場合、大学時代に、民俗学や沖縄地理学の仲松弥秀(やしゅう)先生から教わったことがグソーのイメージに大きく影響している。
みんなの間で「やしゅう~」と、親しみと、尊敬とをこめて呼ばれていたから、
ここでも下の名前で呼ばせてもらうけれど、その生涯をかけた研究は、沖縄の民俗地理学のスタンダードとなっている。特に野外でのフィールドワーク、実地調査を重視していた。

路地裏にも無数のたましいが行きかう、旧盆の夜。 コザ/2012年
「古事記時代までの日本民族は、死後の世界を暗黒の世界としてではなく、現世すなわち“明るさ” と通ずる“黄” の世界としてとらえていたと思われる。
おもろ(古い時代の書物/筆者注)の記述から古代沖縄の色彩観念を質してみると、赤・白・青・黒の四色しか見出せない。このことは奄美諸島も同様であったようである。赤と白は“明るさ” に通ずるが、そのうちの赤は魔物にとっては怖いものであり、しろは清浄に通ずる。黒は赤・白すなわち“明るさ” と対照的な暗黒・無・恐怖・穢れの世界を観念させ、想定させる。
残る青は、青空・青葉・青海の語によっても推測されるとおり、空色・緑・淡黄・碧などの色をあらわしている。そしてこれらの色彩は赤と黒に対して中間色といってよいであろう。
したがって“青の世界” は暗黒でもなければ、赤・白をもってあらわす“明るい世界” でもない。むしろそれは、明るい世界に通ずる淡い世界、古事記の“黄の世界”と類似の世界であると想定されるであろう。 ~中略~ 古代沖縄人は死後暗黒の世界には行っていない。「青の世界」に行っているのである」 仲松弥秀「神と村」より

ばあちゃんをグソーから、じいちゃんが見守っている。
海に潜るために沖縄に来た僕だったが、沖縄国際大学の社会学科に入って、文化人類学や民俗学も学ぶことになった。1989年当時、通称「沖国/オキコク」は“偏差値”という点では全国最下位の大学だった。早稲田・慶応を頂点とする「偏差値表」の一番下に、1校だけ目立っていた沖国を見たとき、僕の人生は変わった。
「この学校だ。ここに行くしかない」校名が光り輝いて見えた。
沖国で出会った先生方はみなユニークそのものだった。「沖縄で」研究することにこだわると、こんなにも深く世界が見えてくることを、先生方は身をもって教えていたのだと思う。その最たる一人が弥秀先生だった。


月が空にある。宇宙にある。
「腰当(くさて)とは、幼児が親の膝に坐っている状態と同じく、村落民が祖霊神に抱かれ、その膝に坐って腰を当て、何らの不安も感ぜずに安心してよりかかっている状態をさしていう。
このように、村落民と何の隔りもなく、親しみより添う、いわば村落民と一体になっている神、これがクサテ森に祀られている神であって、常時村落民と共にあり、これを抱き、護っている、いわば村落民がこの上なく信頼している神である。
この神は、たんに村人の想念のもとに神を招請して、作為的に守護神にしたてあげた神ではない。ではいかなる神かというと、この神は彼ら村人と血のつながった歴史的な祖霊神そのものであり、村人からみた場合は、すべてを投げ捨てて自分たちを抱き育ててきた親々の昇華した神である。このことから子である村人は苦しい時にも、悲しい時にも、また嬉しい時にもこの神に訴え、愛護を求め、信頼し、腰当(クサテ)にしてきたのである。
クサテ森になっているその場所は、作為的に選定された場所ではない。その場所は、そう成るべき所がすでに在ったのである。この場所を一言でいうならば、そこの村人の遠い祖先たちの霊が宿っている、いわば古代の葬所の場所であったのである。
クサテ森といわれているものの中には、必ずといってよいほど納骨された場所がある。この神骨は「骨神(ふにしん)」といわれ、大切に保管されてきたものであるが、今まで秘密にされていたのである。グスクも古代の葬所であったところが多く、そうした場所がクサテ森になっていることは至極当然なことである」 「神と村」より

太鼓のみの道ジュネー(練り歩き)。より古い時代を感じさせる。
この弥秀先生の意見は、グスクをつくったのは誰か、という論争をおこした。沖縄の地域首長にあたる「按司(あじ)」の居城だとする考えと真っ向からぶつかったのである。また、次のようなところに僕は共感する。
「明治以前までは、このようなことは滅多になかったであろうと推定されるのであるが、社会の変化と、それに幸か不幸かは知らないが学校教育の在り方などによって、村の信仰を原始的な軽蔑すべきもの、迷信以外の何物でもないと考える者が次第にふえてきて、神が蔑視されるようになり、神の力に拠った村の行政、団結が、官公吏や知識人に移るにつれて、村の神事が忘れ去られるようになった。
神はいよいよ遠くへ去りつつある。奄美諸島においては、瀬戸内地方以外の地域や島々では、すでに、消滅寸前の状態に瀕し、沖縄本島やその他の島々においても年々失われつつある状態であって、このままではその消滅はただ時を待つばかりと思われる。今、早急に、各島各村落を踏査して宗教的、民俗的な調査をしなければ、後世億円を積んでも、再び死者は舞い戻ることはないだろう。」「神と村」より

この先生の警鐘から、やがて40年近くを迎えようとしている。その後、市町村誌の編纂が進み、調査はひと通り成果を収めた。間に合わなかったものも多々あるだろう。だが、沖縄が今でも沖縄らしさを失っていないとするならば、この沖縄で培われてきた精神世界は、今の世を照らす一筋の光になりうる気がするのだ。現代にひろがり深刻さを増す悩みの多くを考えると、自分を無条件で愛してくれる存在のなさが、大きな原因のように思える。
祖霊神=ご先祖さまは、自然と一体になった存在である。自然は、地震の時も津波の時も、人を個人で区別しない。容赦なく命を奪っていく。どんなに僕らが「生きていてほしい」と願う人であっても、それは変わらない。それを「無常」と呼んだりする。
だが一方で自然は、人間を生きものの一部として、今も新しい命を誕生させている。生物学であれ、民俗学であれ、長く自然を見てきた者はひとつの結論に達するのではないだろうか。「いのちはつながり、めぐっている」という真実である。
人が生まれてくることは、自然にいつか還ることと、たぶん同じことなのだろう。それは必然的に僕たちの生を肯定し、孤独の苦しみから遠ざけてくれる。

家族親戚みんなで、おばあのやり方を見守る。南風原/2008年
弥秀先生は2006年、98歳で亡くなられた。95歳まで教鞭をとっておられたという。ご病気になったあとも、最期まで古えの沖縄のイメージを追い求めていたに違いない。みんなでマイクロバスに乗って、南部に点在する拝所めぐりをする
「東御廻い(あがりうまーい)」に出かけたのが先生とお話した最後の日になってしまった。
杖をつきながら、階段もヨイショヨイショと登っていく健脚を見せ、学生が労わると「気にするな」と言わんばかりに説明に熱を入れる。「スッサー!やしゅう~」(弥秀は凄い!)と学生が舌を巻くほどであった。僕が撮影したザトウクジラの拙い写真を得意げに見せると、「おお~!」と同じ目線で喜んでくれたりした。
首里にあるご実家へ訪ねてみたい、という想いは叶わなくなってしまったが、「神と村」(伝統と現代社/1975年、梟社/1990年)「うるまの島の古層―琉球弧の村と民俗」(梟社/1993年)「古層の村―沖縄民俗文化論」 (沖縄タイムス社/1977年)などの著作を読み返すと、沖縄の精神世界を立体的に解き明かそうとした弥秀先生のロマンと気概が伝わってくる。
静かな授業で眠っている学生も多かった教室で、「御嶽(ウタキ)は神社の先輩なんだよ~」と講義のたびに語っていた弥秀先生と、一度じっくり話をしてみたかったと思う。
※ウタキ…御嶽。古代沖縄の信仰上の拠点。古墓を擁した森や林であることが多い。
現在では祭祀施設が作られていることもある。

*
そして2012年。今年の旧盆の初日、ウンケーは、ばあばやじいじたちと行なった。しーちゃんは花火を楽しみにして、そわそわと落ち着かない。ばあばの営む古本屋の奥にオリジナルの仏壇がある。仏壇といっても、仏教とはあまり関係なく、
沖縄の大家族が維持しているような、何個も並ぶトートーメー(位牌群)でもなく、ごく個人的なものだ。「ご先祖さま」というよりは、「家族の記憶」そんな感じがする。

32歳で亡くなった義姉、トキオのお骨もそこにある。僕が以前撮った、彼女が森に溶け込んでいくような写真も飾られている。その前に座ると気持ちが落ち着く。自然と、最近の夫婦仲の報告などをしているのだ。
僕の部屋にも、祖母のお骨が小さな陶器に入れて置いてある。ふだんはほとんど忘れているけれど、ふとした時に開けて手にとってみると、その乾いた感触に安堵を感じる。お骨を置いておくと、「成仏しないから可哀想」という方もいるけれど、この世から去ったあとの道筋は、愛する者に任されていいのでないかと思う。
死後、僕たちが決まった形で存在しなくてはいけないとしたら、生きている今そのものさえ自由ではなくなるだろう。
人は自然の多様性の一部である。千差万別であることにこそ、価値があるのではないだろうか。


しーちゃんとみんなで花火をした。
線香花火の微かな光に子どもの頃の記憶が甦る。
あっというまに3日間の旧盆の最終日、ウークイを迎えた。うちの家族は南風原に集合だ。といってもきっちりではなく、あくまでもゆるりと集まる。みなで拝んだあとは、“ウサンデー” をする。お供え物をいただくのである。これが昔の子どもたちには楽しみだった。今はモノがあふれているから、欲しがる子も多くはないけれど、「ウサンデーするとご先祖さまに守ってもらえるよ~」と言えば、たいがいの子は素直に手を伸ばす。ウーマクー(生意気盛り)の子どもたちにも、目に見えない世界のことはちゃんと伝わるのだ。

新しい命の誕生と。
南風原でのウークイを終えたあと、妻とコザに帰った。8月の長い夕暮れが、時間の感覚を迷わせる。腹時計と相談しながら夕食にした。夜の帳がおりるころ、遠くから歌とサンシン(歌三線)の音が流れてきた。毎年旧盆が近づくと、エイサーの本場コザには太鼓や唄サンシンの声がひびく。
これまでは、明るい会場でエイサーを観ても、心底惹かれたことはなかった。
だが今夜は違っていた。妻とトキオのことをいろいろ話したからかもしれない。トキオは東京でエイサーをやっていた。それに、昼の時間の過ごし方がゆったりとしていたからかもしれない。闇の音に導かれるように、僕はカメラを手に外へと出た。エイサーを通じて、まだこの街に残る暗闇を撮りたかった。

子どもたちがジウテー(地謡)をこなす。大人と向きあって。



近年エイサーは芸能として年中行なわれるようになっているが、源流は念仏踊りだといわれている。ご先祖さまをグソーへお送りするための儀式なのだ。それだけに、今でもウークイのエイサーは特別である。
集落に街灯がまだない時代から、年長者たちは青年会でエイサーを通じ、子どもたちに大切なことを伝えてきた。
自分が今あることに感謝すること。心を鎮めること。闇と月の力を借り、魂をこめて舞うこと。
子どもは期せずして、自身や自然との対話をもちながら育つことができたのだと思う。

OBが若手をしっかり支える。



月明かりの下、街灯のない路地裏をひたすら舞い歩く。
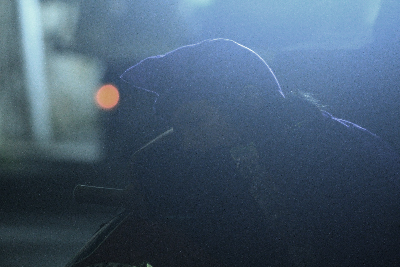
深夜になった。練習の日々の延長にある今夜。
沖縄は夜型社会だという。コザでは確かに深夜、外にいる青少年たちの姿は多い。嘉手納や普天間からの米軍ヘリが真夜中に飛び、学力は下位。夜勤の親も多く、社会人になってもアルバイトでは最低賃金625円。子どもたちの環境は良いとはいえない。だが沖縄の子たちはすばらしい。なぜかそう誇って言えるのだ。その理由を、ずっと考えてきた。


繰り返しが何かを生んでゆく。

震災と、予想通りの原発事故の後、沖縄から日本という国を見ていて腑に落ちたことがある。それは、沖縄では「夜の力」が子どもの根底に届く余地がまだある、ということだ。
「夜」とは一言でいえば、畏怖を教えるもの。人智を超えた存在を受け入れることで、謙虚さ、思いやり、責任感、そんなまっすぐで恥ずかしくなるような、けれど、なくてはならない物ごとを学ぶことができる。人は何でもできる、というような思い上がりは、そこからは生まれない。
「明るい社会」のために、原発さえも推進してしまう人々や、「生きている重さ」を想像できなくなってしまった子どもたち。そのいずれもが、畏怖を忘れた社会に端を発しているように、僕は感じている。

記憶の積み重ねが、この子の将来を創っていく。



子どもにとって夜は、昼の窮屈な空間から自分を解き放つことができる時間。
沖縄では飲酒で捕まる未成年も多いが、彼らは海が大好きだったりする。月明かりの下、海風に当たりながら仲間と話をする。大人も深夜俳諧は指導するが、夜の暗闇そのものや彼ら自身を否定はしない。
沖縄でも暴力事件は起きている。それでも子どもたちを見捨てず、同じ目線で向き合う大人がいて、ウザイと言われても関わり続ける。それがこのシマの懐の深さを生むのだと思う。


魂を込めて舞う。必要なのはそれだけだ。

エイサーの練習は楽しいけれど、楽ではない。仕事や学校でクタクタの夜も、毎晩のように練習が続く。教える先輩や長老は口うるさい。けれど子どもたちは、夜の闇が支配する路地裏で、ピアスをした青年たちの流す汗に何かを感じ、ひたすら舞い続ける姉さんたちの姿を、食い入るように見つめる。
ここでは、大きくなって青年会で汗を流している自分を想像することができるのだ。大人になった自分のかたわらには、素敵な彼や彼女もきっといることだろう。


そう。「大きくなったとき」。その姿を子どもたちがイメージできる世界を取り戻すことはできないだろうか。ただ明るさのみを追求するのではない、暗闇を大切にできる社会を取り戻す。弥秀先生が語っていたように、表に出ないことを想像し、尊び、目に見えない世界を大切にする。たくさんの悲しみや怒りを抱え、迷いながらも、沖縄はそのことを模索している気がする。


サッカーに秀でた青年も、今はこの空間の一部になった。


役目を終えた後の顔が、すべてを物語る。

ふだんの中学生や高校生に戻っていく。


数日後、美里(みさと)の公民館に足を運んだ。エイサー中に知り合った金武(きん)正博さんに、撮った写真を届けるためだ。
正博さんは美里青年会のOBである。
「エイサーが好きで好きで。いろいろ子どもたちに教えたりもしているんです。美里のエイサーは歴史が古いんですよ。派手な動きのほうにみんな(若者は)行ってしまうんですけどね~」
正博さんの地元への思い入れが伝わり、気持ちがよかった。古き良きものは、少なくなっても、また誰かが息を吹きこむ時が来る。それは心配しないでいいことのように思えた。公民館の庭からは、この夏最期の花房を下げたサガリバナの、
湿った香りがやんわりと流れている。旧盆も終わり、季節は秋の気配を見せ始めている。ひんやりとした夜気に、コノハズクの啼く声が聴こえていた。

正博さんの家にジウティのメンバーが集う。ウークイエイサーの写真と、今日の釣果で作った魚汁を肴に。

ご先祖さまのための家。旧盆の名残でまだ明かりが灯っていた。
Essayへ戻る
第6回・サバニ大工 ~糸満うみんちゅのこころ~ その1
累計:5560 今日:1 昨日:0